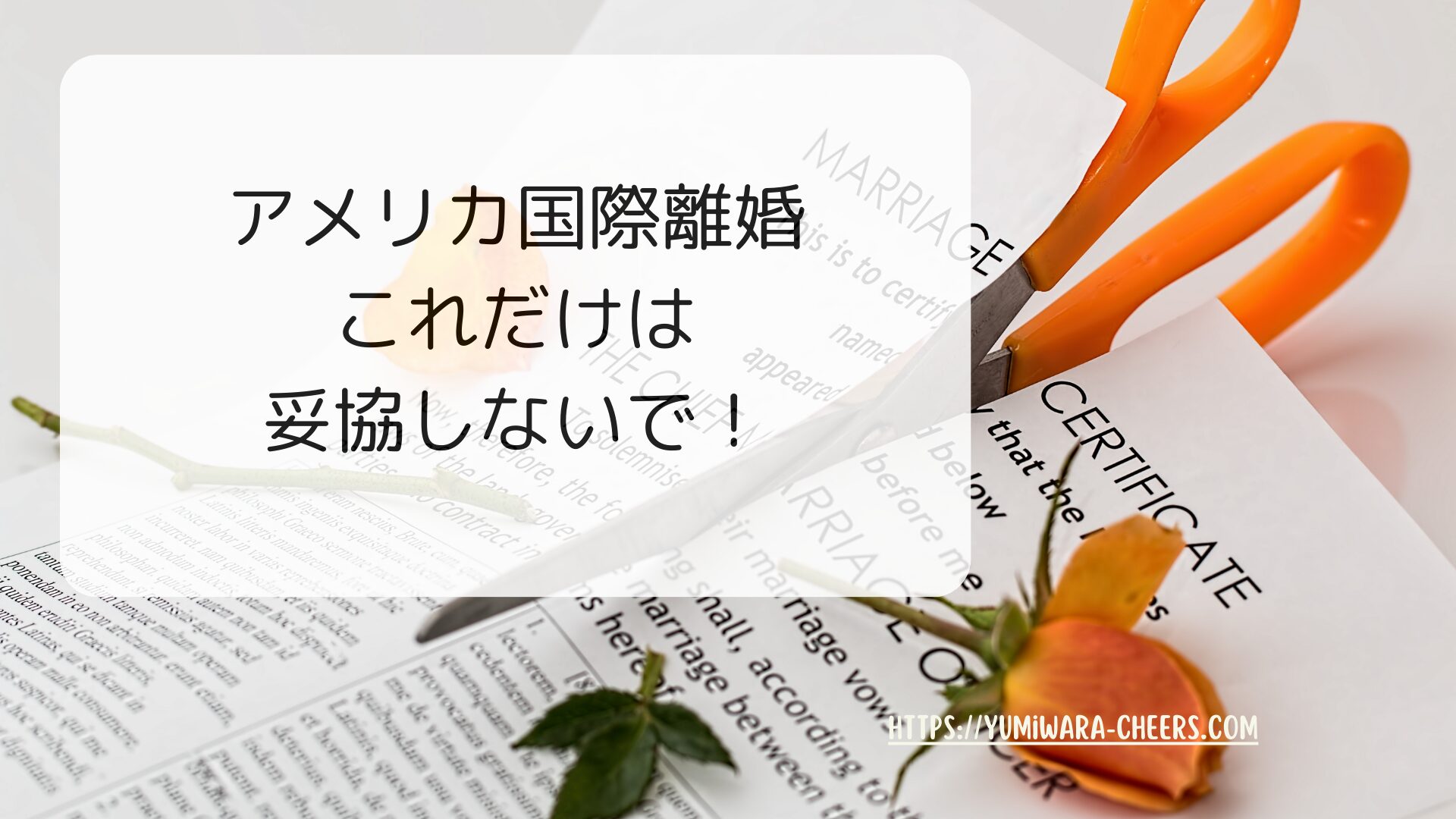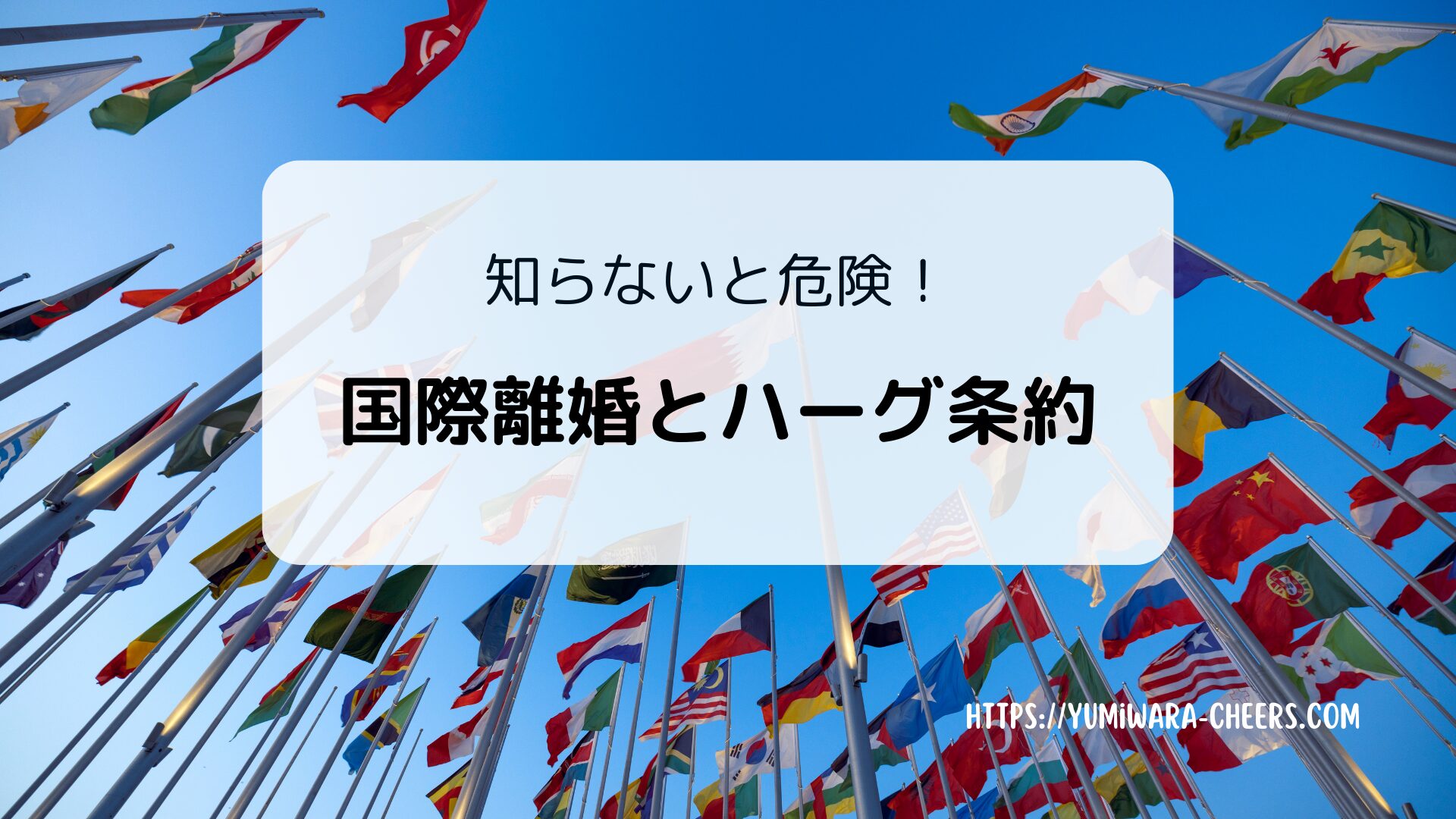本日もお疲れさまです!
こんにちは オレゴンから ゆみです
おかげさまで、今日も元気でやってます。
国際結婚しててね、誰しも一回くらいは離婚がよぎったことってあると思うねんやんか。ましてやそこにDVがあったりしたら尚更のこと。頭の中で数えきれへんくらいのどうしよう? がある中で、子供を連れて日本へ帰ることができたらなぁって願うと思うねん。
私も同じことめっちゃ考えたもん。
でもね、ハーグ条約があるから勝手に連れ帰ることはできへんのよ。
きっと一度は聞いたことあると思う『ハーグ条約』のことを今回は一緒に学んでいきましょう。
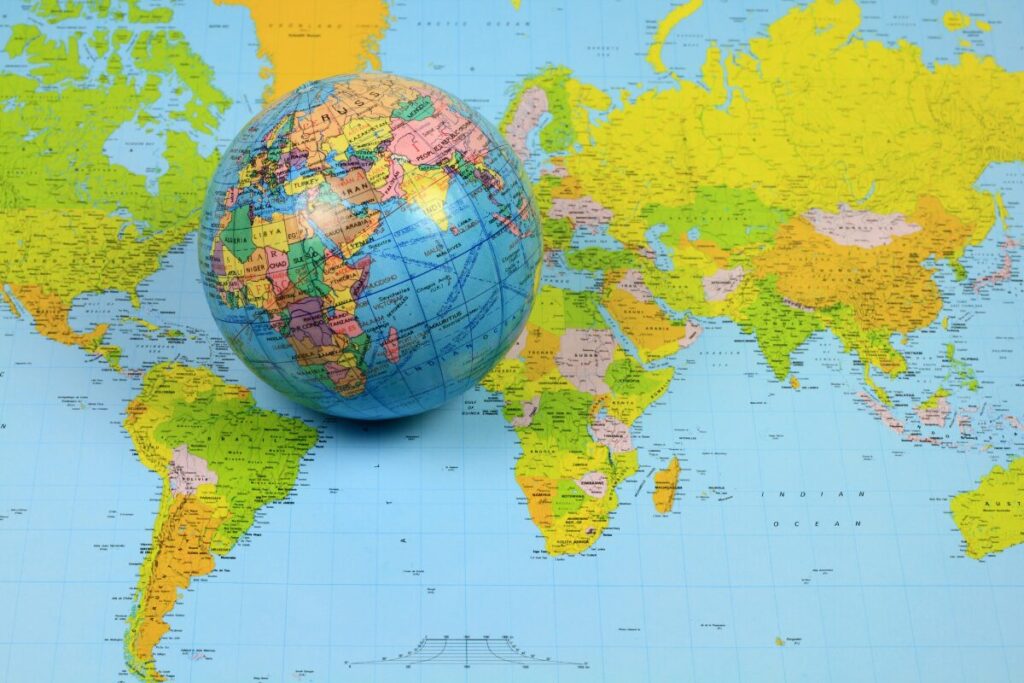
ハーグ条約の基本:目的と仕組み
目的は、子供を「元の生活」に戻すための国際ルールです。
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)は、
国際結婚や離婚に関わる親の一方が、もう一方の親の同意なしに子どもを海外へ連れ去ってしまうことを防ぐための条約です。
この条約は、親同士の権利争いではなくて子供を元の生活環境(習慣的移住地)に戻すことにあります
例えば:子供はアメリカで学校へ通ってるのに母親が日本へ子供を連れ帰ってしまう
この場合、日本の裁判所は「親権は誰にあるか」ではなく、まず 子どもをアメリカに戻すべきかどうかを判断します。
習慣的居住地とは?
条約では「子どもが普段生活していた国」を 習慣的居住地 と呼びます。
ここが基準になり、原則として その国で親権や養育を決める べきとされています。
👉 つまり、引っ越しや転校などで一時的に滞在していた国は含まれません。
仕組み:返還までの流れ
1:連れ去られた親側が申請します
被害を受けた親は、自国の「中央当局」に子どもの返還を申請。
例:アメリカなら国務省、日本なら外務省。
2:国同士でやり取り
アメリカ国務省 ⇔ 日本外務省(中央当局)間で連絡・調整。
3:裁判所が審理
連れ去られた国(この例では日本)の 家庭裁判所 が「返還すべきかどうか」を判断。
4:返還命令 or 例外適用
原則は「元の国へ返還」ですが、
- 子どもが大きく成長して環境が変わってしまった場合
- DVや虐待の危険があるなどの場合は例外が認められることもある。
子どもが海外へ連れ去られた
↓
中央当局に返還申請
↓
連れ去られた国の裁判所が審理
↓
原則:子どもを「元の国(習慣的居住地)」へ返す
※親権争いは元の国で行う
返還命令と親権は別問題
ここが誤解されやすいのですが、親権は関係なくて
ハーグ条約で裁判所が判断するのは 返還するかどうか だけです。
⚠️ 親権・養育権の最終判断は、子どもの 習慣的居住地の国の裁判所 が行います。
👉 要するに
「どっちの親がいいか」ではなく 『子どもはまず元の国に戻す』 というのがハーグ条約の考え方です。
返還命令が出ない『例外』
❌ 子どもが重大な危険にさらされる場合
- 連れ戻された国に帰ると、身体的・精神的に害を受けるおそれがある
- 例:虐待・DVが明らかにある場合
❌ 子どもが返還を強く拒否している場合
- 子どもがある程度の年齢と成熟度を持ち、
自分の意思で「帰りたくない」と強く表明しているケース
❌ 申請が遅れた場合
- 連れ去りから 1年以上経過 しており、
子どもが新しい環境にすでに適応している場合
❌ 親が同意していた場合
- 連れ去りや滞在延長に、実は同意していたと認められる場合
『例外』はあくまでも特別なケースです、多くのケースでは、やはり「元の国に戻す」が基本ルール。例外を主張するには、連れ去った親側が 証拠をしっかり示す必要 があります

ハーグ条約 加盟国と非加盟国の違い
このハーグ条約は世界中の国が加盟しているわけではありません。
ちなみに日本は2014年にハーグ条約加盟国になりました。
加盟国(ハーグ条約を締結している国
現在、103の国と地域がこのハーグ条約に加盟しています
加盟国同士の場合、子どもが親の一方によって同意なく連れ去られた時には、中央当局を通じて返還申請が行われ、裁判所の判断により返還命令が出される可能性があります
加盟国同士なら、共通ルール に基づいて子どもの返還を求められる。
日本とアメリカはどちらも加盟国なので、もし片方の親が子どもを無断で連れ去った場合でも、返還申請 → 裁判所 → 返還命令 という流れで解決を図れる。
加盟国では「中央当局」が必ず設置され、相手国との調整をサポートする。
日本:外務省 外務省ハーグ条約
アメリカ:国務省 国務省ハーグ条約
👉 メリット:国際的に子どもの権利を守る仕組みがあるので、返還の可能性が高い。
非加盟国(ハーグ条約を締結していない国)
この場合、ハーグ条約の制度自体が使えないため、国際的な返還手続きは成立せず、子どもを取り戻すのは非常に困難です。
アメリカ側で「親による国際誘拐罪」などの刑事措置が取られる可能性はありますが、子どもの返還とは直接関係しないため、別の問題となります
条約の仕組みが使えないため、国際的な返還請求はできない。
子どもを取り戻したい場合、相手国の 国内法や裁判所の判断 に頼るしかない。
相手国の法律が「返還」を認めなければ、子どもは戻ってこない可能性が高い。
アメリカなど一部の国では、親による連れ去りが「国際誘拐罪(IPKCA)」として刑事事件になる場合もあるが、刑事罰と子どもの返還は別問題。
👉 デメリット:手続きが複雑で長引きやすく、返還はほとんど期待できない。
具体的な違い
| 項目 | 加盟国の場合 | 非加盟国の場合 |
|---|---|---|
| 国際的返還ルート | あり(中央当局→裁判所→返還命令) | なし(その国の法律だけが頼り) |
| 返還の可能性 | 高い | 極めて低い |
| 親の刑事責任 | 条約では扱わない(国ごとの法律による) | 国によっては「誘拐罪」として刑事事件に発展する可能性あり |
| 子どもの権利保護 | 国際ルールで守られる | 決まりが違う国ごとの裁量、 |

日本とアメリカの事例
過去に実際にあった事例の中で子供の意思が尊重されて、最高裁まで行った例です。
1. 日本最高裁の事例(2017年決定)
2014年、日本人の母親がアメリカで生活していた4人の子どもを「一時帰国」を理由に日本へ連れてきました。当初は一時的な滞在と合意していましたが、その後も日本に留まり続け、父親はアメリカから子どもの返還を求める申立てを行ったそうです。
この4人の子どもは当時 上の双子:11歳7か月、下の双子:6歳5か月
- 2016年:返還命令確定
日本の裁判所は「不法な連れ去り」と認め、4人全員をアメリカに返還するよう命じました。 - 2016年:強制執行を試みるも失敗
執行官が子どもを返還しようとしましたが、子どもたちが強く拒否し、実際にアメリカに戻すことはできませんでした。 - 2017年:返還命令の取消し
その後の審理で- 上の双子(11歳)が一貫して強く返還を拒否している
- 下の双子も消極的である
- 兄弟を分離させるのは子どもの利益に反する
- 父親は住居を失い、経済的基盤も悪化しており、返還先での養育環境が十分ではない
などの事情が認められました。
これを理由に、大阪高裁は「返還命令を取り消す」と判断。
- 2017年12月21日:最高裁が支持
最高裁も大阪高裁の判断を維持し、返還命令の取消しが確定しました。
(出典:米国議会図書館 loc.gov)
この例は、子供の年齢が意思表示ができる11歳だったことと、父親の環境が子供達にとって良くないと判断されたことで、子どもの意思が強く尊重されることを示した、日本での初めての最高裁判断の一つだそうです。
まとめ
国際結婚、離婚はただでさえ労力が半端なく大変です。ここに『子供の連れ去り』が加わると想像以上に複雑なことになってしまいます。
今回この記事を書くにあたって、ママ側が日本へ子供を連れて帰りたい目線で記事を書いていたのですが、記事を書き進めていくうちに、もし子供の父親の出身国が『ハーグ条約非加盟国』だったら?そして彼が国に子供を連れ帰ってしまったら、子供を取り返すのはとても難しんだと気づきました。
そうならないためにも、国際離婚の際は必ず弁護士をつけて、国外に連れていく際の約束事も決めてください。
子供を「連れ帰りたい」という気持ちはよくわかります。でも、知らずに動いてしまうと、思わぬトラブルや「誘拐扱い」になってしまったら、親権も失ってしまうかもしれへんし、子供にも会えなくなってしまうかもしれません。
だからこそ、まずは「ハーグ条約とは何か」を知っておくことが大切です。
知識があるだけで、いざという時の判断や対応が大きく変わります。
このブログが、少しでも「知らなかった」を「知ってよかった」に変えるきっかけになれば嬉しいです。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。