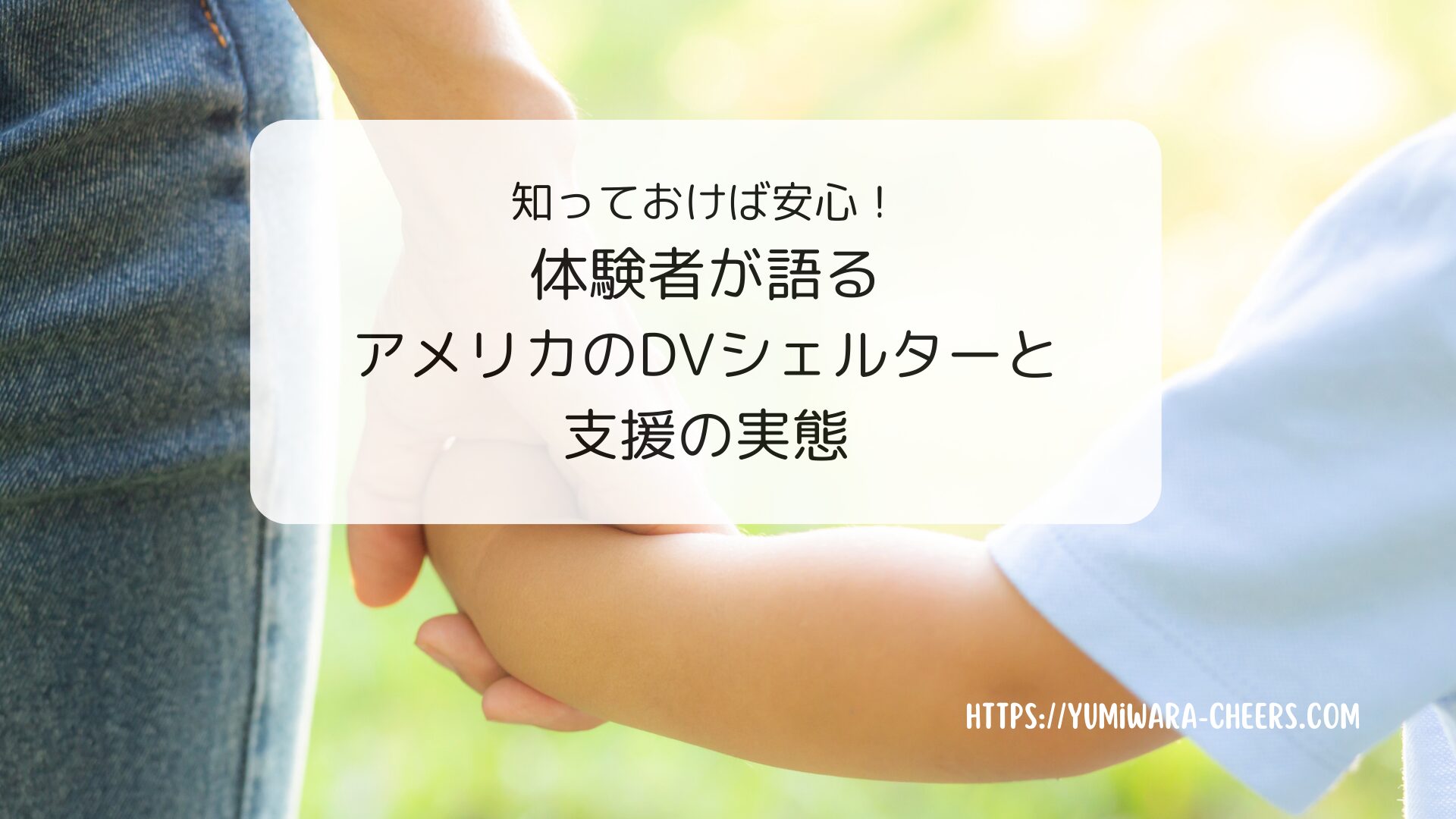本日もお疲れさまです!
こんにちは オレゴンから ゆみです
おかげさまで、今日も元気でやってます。
私は今から10年以上前に2歳の息子を連れて元旦那の家を出ました。
家を出ると決心するまでに、2年以上かかったことを覚えています。行くところもないし、どうやって生きてくのか? 子供はここにいた方が幸せなのか?もう毎日来る日もくる日も行き場のない答えに悩んでいました。
お金も英語力もスキルもないし、近くに家族がいるわけでもない。でもこのままここにいたら、私は○殺するか生き地獄を過ごすのか?ってでも勇気がなくて、行動に移すまでにすごく時間がかかってしまいました。
そんな中、知ったのは行政の支援の一つシェルターでした。その存在は知っていたけどどんなところなのか?どんな人たちがいるんだろうって不安でした。
そんな不安が少しでも解消されたらいいなと思い、シェルターでの当時の話を交えて受けられる支援のお話をします。

アメリカは州によってまたお住まいの郡によってもルールが違います。
シェルターとはどんなとこ?
私と息子はシェルターと連帯する支援施設からの紹介でお世話になることになりました。ちなみに私たちが住んでいたシェルターは高級住宅地にある大きな一軒家でした。
入所前から 必ず守るようにと言われた事がありましたそれは 場所を絶対口外しない
これは、入所者の身の安全を守るための絶対ルールでした。
1. シェルターの入所基準
多くのシェルターは DV被害者とその子供 を対象としています。ただし、シェルターによっては 人身売買の被害者、性的暴行の被害者、ストーカー被害者 なども受け入れている場合があります。
DV被害者であることが前提(多くの場合、警察の報告書や保護命令がなくても受け入れ可能)
シェルターのルールに従う意思がある(共同生活になるため)
加害者と連絡を取らないこと(安全確保のため)
薬物やアルコール依存がない、もしくは治療中であること(リハビリ施設を案内されることも)
入所のプロセス
- ホットラインや支援団体に連絡
- まず、DV被害者支援団体やDV ホットライン(National Domestic Violence Hotlineなど)に相談。
- シェルターの空き状況を確認し、受け入れ可能な場合は面談へ。
- 簡単な審査と入所面談
- 過去のDVの状況や、現在の安全性について質問される。
- 持ち込み可能な荷物やルールの説明を受ける。
- 移動・入所
- シェルターの場所は基本的に秘密。
- 自分で移動するか、場合によっては支援団体が送迎を手配。
2. 滞在期間の制限
一般的に 30日〜90日
ただし、状況により延長が可能な場合も。
長期的な支援が必要な場合は、トランジショナルハウジング(移行住宅)や支援プログラムに移ることも。
私と息子は90日間お世話になりました、のちに移行住宅の申請をしてシェルターを後にしました。
3. シェルターの規則
外部との連絡制限(加害者から身を守るため)
門限や外出ルール(安全のため、事前に許可が必要な場合あり)
アルコール・ドラッグの禁止(他の住人の安全確保のため)
シェルター内での、飲酒は禁止です、もちろんドラックもダメです。
門限や外出時の行き先の報告。
4. シェルターの支援内容
安全な住居の提供 (外部からはわかりにくい場所にあります)
食事や生活必需品の支援 (洋服や日常で必要な消耗品も)
法的支援(離婚、保護命令、子供の親権などの手続き)
カウンセリング(PTSDやメンタルヘルスのケア)
自立支援プログラム(仕事探し、英語教育、スキルアップ)
シェルターでの滞在中に受けることができる、基本的な支援です。身の安全を守るためにしっかりとした防犯設備が整っています。
食事の支援は、一般家庭にある基本的な常備食があり、共同キッチンにて料理を作ることもできました。
私がお世話になった施設では、私が初めての日本人だったため必要な調味料とかのリクエストも受けつていただけました。
1日の生活
ミーティング
朝は決まった時間までに起きて、リビングに集まるという約束がありました。
これには、規則正しい生活を送るという意味もありますが、その日の気持ちのシェアや施設の方からのDVに関する話や
同じ境遇にある人の話を聞くことで、客観的に自分を見るきっかけになるための時間でもありました。
掃除
各部屋の掃除以外に、共同スペースの掃除を入居者がします。スケジュールは基本施設の方がしますが、入居者の入れ関わりがあるため、その都度話して決めていました。例えば、リビングに掃除機、階段の清掃、水回り、玄関といったように分担をしていました。
カウンセリングやサポートプログラム
- DV被害者向けのカウンセリング、グループセッション等
- 就職支援、法的手続きのサポートも受けられる。
私はここで息子のプリスクールの手続きの支援を受けて、息子を預けることができました。
DVの加害者と被害者の関係性等も学ぶことができたおかげで、私は戻ることはせず今に至ります。
自由時間
- 共同スペースで過ごしたり、部屋で休んだり。
- 仕事がある人は出勤
- 門限や外出制限はありますが可能です。
シェルターに逃げてきた人達
私がお世話になった3ヶ月間の間には、いろんな人が出入りしていました。
年齢も家族構成もみんな違ったし、何があってきたのかも違います。
朝に来て夕方には出て行かれた方、一晩だけ子供を連れて逃げてきた方、ここに来るのが3回目だといってた人もいました。
Cさんの場合 20代の彼女は同棲していた彼らの暴力から逃げてきていました。母親とは絶縁状態で行くところがなくの決断でした。彼女は次の日にでも彼のところに戻るところでしたが、DVの被害者と加害者の関係性の話を聞いて思いとどまり1ヶ月ほど過ごし、仕事を見つけてシェルターを後にしました。
Eさんと3人の子供の場合 Eさんと3人の子供はある日の夜、着の身着のままの状態でやってきました。一緒に生活してた旦那さんが重大な犯罪を犯しているということが分かり、恐ろしくなり逃げてきたのです。何を犯したかは知りませんが彼は逮捕され Eさんと子供達はシェルターを後にしました。
SNSで見る彼女は現在とても幸せそうで、先日あの当時小さかった娘さんがママになり彼女がおばあちゃんになったことを知りました。
ママと2人の子供とおばあちゃんSさん おばあちゃんといっても50代後半、今の私の年齢くらいの方だったと思います。彼女らもある日の午後やってきたのですが、彼女たちの入所と同時に部屋の配置が変わりました。彼女らは本宅の横にあるゲストハウスの一部屋、私はその彼女らと向かいのベッドだけがある部屋に移りました。バスとトイレを共有することになったのはいいのですが、私物は個々保管することになっているにもかかわらず、全ての物が出しっぱなしでまあひどい。でも仕方がないと何も言わなかったのですが、ある日二日続けてカミソリがそのままシンクの横に出したままでした。これには子供にとって危険だと思い、優しくお願いしましたが反対に逆ギレされたのです。最初から施設の人に報告するべきだったと当時思いました。しかしこの件以外にもルール守っていなかった彼女らはシェルターを出なければいけなくなったのです。
今でも鮮明に思い出すのが彼女らがシェルターを出る時、ガラス窓越しにおばあちゃんSさんに
FプラスBワードを指までつけて叫ばれたのよー私!
今となっては思い出の一つですがその時はただでさえ弱っていたメンタルに刺さりました。
この家族以外は、みんな何らかの理由で逃げてきてるからお互いに干渉せずにも
痛みを分かち合えてた気がします。
施設の人曰く、滅多にない事例だといっていました。
シェルター滞在中に仕事に行くことは可能?
仕事に行くことは可能 です。ただし、シェルターごとにルールが異なり、以下のような点に注意が必要です。
安全確保のための制約:
シェルターの場所は周りに知られてはいけないので、通勤ルートや勤務先を慎重に管理する必要があります。
・加害者に知られないよう、職場の住所を伏せる努力が求められることも。
・一部のシェルターでは、出入り時間の管理や、スタッフへの報告が必要な場合も。
・Uberやタクシーなどを利用し、直接シェルターの近くで乗降しないようにする。
仕事を探すためのサポートもあり:
シェルターには、被害者の自立をサポートするプログラムがあり、履歴書の作成や職探しのサポートをしてくれるところも多い。
仕事を探している場合、シェルターの支援スタッフが求人情報を提供したり、就職支援センターを紹介してくれることも。
シェルターを出た後の保証はある?
あります!主なその後の生活のサポートは
移行住宅(トランジショナルハウジング)
・通常のシェルターよりも長期間滞在可能な住宅支援制度。
・家賃補助があり、一定の収入があれば少額で住める場合も。
・生活の安定に向けたプログラム(カウンセリング、就職支援、家計管理サポートなど)が含まれる
政府・NPOの支援
・Section 8(低所得者向け住宅補助) や TANF(低所得家庭支援プログラム) を利用できる場合がある。
・食料支援(SNAP)や医療補助(Medicaid)を受けながら生活を再建できる。
・シングルマザー向けの支援団体が、自立のための家探しや育児サポートを提供していることも。
法的支援の継続
・離婚や親権問題が解決していない場合、シェルターを出た後も弁護士のサポートを受けられるケースが多い。
・ストーカー対策や保護命令の延長なども支援団体を通じて相談できる。
私はほぼ全ての支援を受けることで、異国の地で家族もいない中
息子との安心した生活を手に入れることができました。
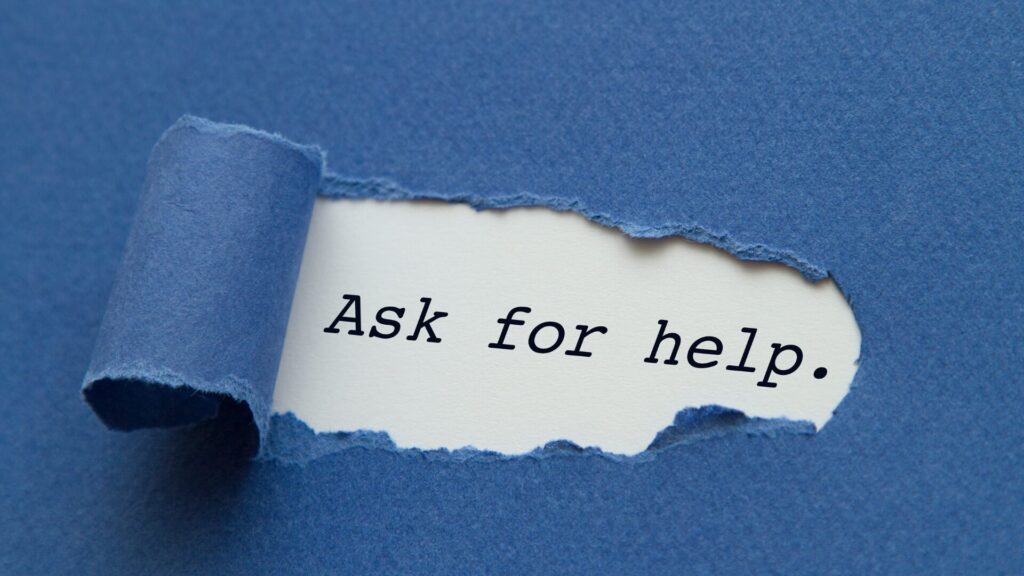
7コールルール(7 Call Rule)
この言葉を聞いたことがありますか?
アメリカの警察やDV支援団体の一部で言われる概念で
DV被害者が警察や支援機関に助けを求める回数に関するものです。DV被害者は、逃げる決断をするまでに平均7回、警察や支援機関に助けを求めると言われている。
しかし、7回目の連絡ではすでに命の危険が高まっているケースが多い。
そのため、1回目や2回目の時点でできる限り早く支援を受け、安全確保をすることが大切。
この話は何度も聞きました、シェルターにもこの事例を例えるポスターが貼られていました。
警察や支援機関の視点
1回目の通報の時点で支援を受けることが重要。
警察は「またすぐに戻るだろう」と思い、すぐには本格的な介入をしないこともある。
DVはエスカレートするため、「次こそ大丈夫」と思わず、早めに逃げる準備をすることが生存率を上げる。
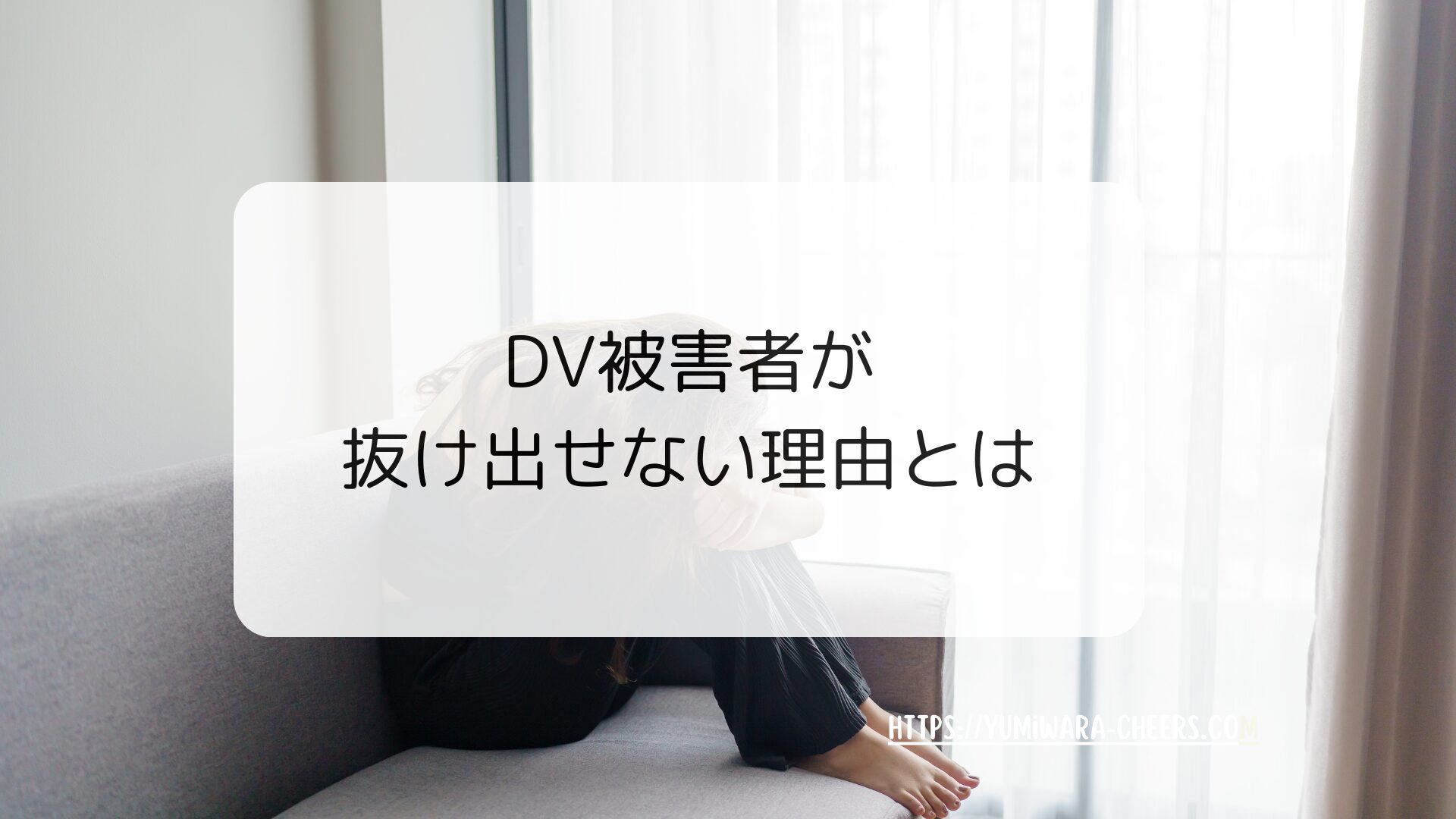
まとめ
行政に助けを求めることは勇気がいることかもしれませんが、異国の地で頼る家族もなくこの先の生活を考えた時、行政に頼る選択肢は必ず大きな支えになります。
シェルターって聞くと、がんじがらめで規則が厳しいイメージがあるかもしれませんが、私の経験からはそれはほぼ感じませんでした。
何かあってからでは遅いです、この記事に辿り着いた人は何らかの理由があって読んでくれたと思います
自分のお住まいの支援団体等を調べてお句ことをお勧めします。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
この記事があなたの一歩につながりますように